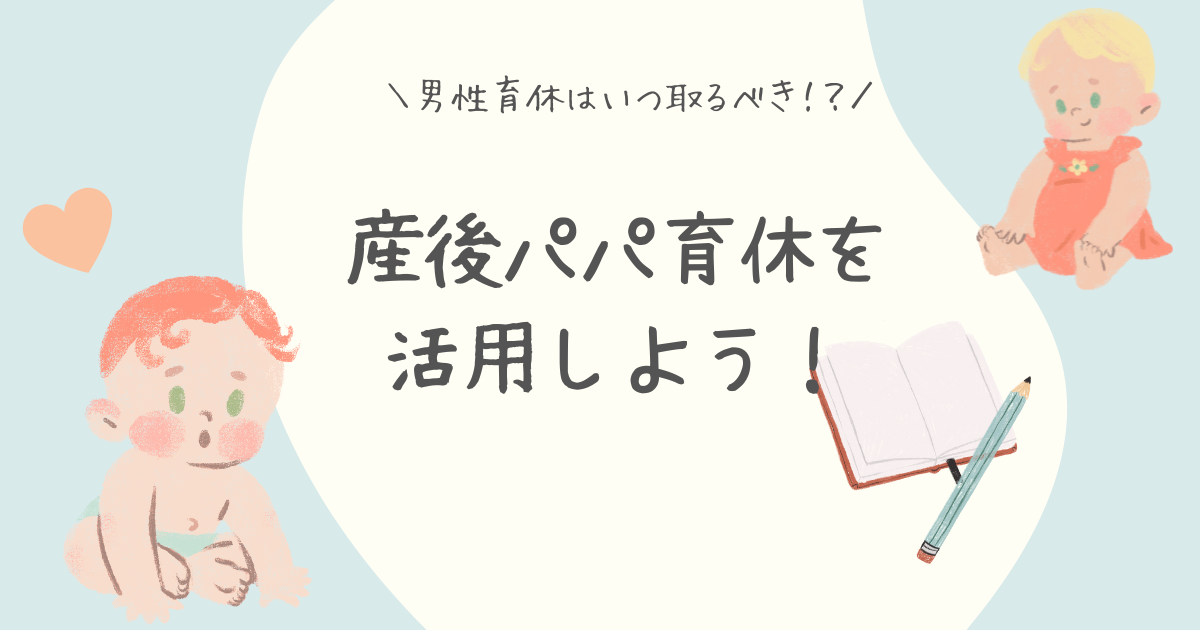2022年10月に「産後パパ育休(出生時育児休業)」という新しい制度が施行されました。
産後パパ育休の目的は、男性の育児休業取得率の向上と、男性の育児参加を促進することにあります。
産後パパ育休に、従来の育休も併用すると、最大で4回にわけて育休を取得できます。
これまでは、女性が取得するイメージが強かった「育休」。
「どうやって使えばいいの?」「どのタイミングで取るのがベスト?」と悩む男性も少なくないのではないでしょうか。
今回は、産後パパ育休の詳しい内容や、育休活用方法について詳しく解説します。
産後パパ育休とは
「産後パパ育休」は、正式名称を「出生時育児休業」といい、2022年10月より施行された制度です。子どもの出生後8週間以内に、4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できます。
産後パパ育休と育休はどのように違うのか、以下の表にまとめました。
| 制度の名称 | 産後パパ育休 | 育休(育児休業) |
| 対象期間 | 子どもの出生8週間以内 | 原則、子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで) |
| 取得可能日数 | 原則4週間以内 | 柔軟に設定可能 |
| 対象となる人 | 父親(養子の場合、母親も可能) | 父母どちらも可能 |
| 給与(雇用保険) | 育児休業給付金あり(原則休業前賃金の67%) | 育児休業給付金あり(原則休業前賃金の67%→6ヵ月後から50%) |
| 取得手続き | 原則2週間前までの申請 | 原則1ヵ月前までに申請 |
| 分割取得 | 2回まで可能 | 2回まで可能 |
産後パパ育休と育休では、対象となる人や申請できる期間が異なります。
また、2025年4月から新たに「出生後支援給付金」が創設されました。
出生後育児休業支援金は、子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間支給されます。
男性の場合、出生後支援給付金が支給される対象期間は「産後パパ育休」の期間です。
産後パパ育休の給付金と合わせると雇用保険の給付率が給与の80%(社会保険料が免除されるため、実質手取りは100%相当)になります。
産後パパ育休を「いつ」取るべきか
産後パパ育休は、出産の際に里帰りをしない家庭の場合は特に「出生後すぐ」取得することがおすすめです。
出産後約6~8週間頃は「産褥期」と呼ばれ、妊娠や分娩によって変化した身体が元に戻るまでにかかる期間です。
この時期のママは、赤ちゃんの世話をする時間以外はゆっくりと身体を休める必要があります。
したがって、出産後に必要な書類の記入や提出、上のお子さんの世話などをパパが代わりにすることが望ましいです。
さらに、出生直後からパパが育児に積極的に参加することで、赤ちゃんとの絆を早期から構築できるというメリットもあります。
また、産後パパ育休は2回に分けて取得できます。
里帰り出産をする家庭の場合は、出生後書類の提出のために一度取得し、間をあけてママの実家から帰ってくるタイミングでもう一度取得するといったパターンも可能です。パートナーや職場と相談して、各家庭の状況にあったタイミングで取得するとよいでしょう。
時期別!産後パパ育休の有効活用法
産後パパ育休は、具体的にはどのようなことに活用できるでしょうか。
ここからは、産後すぐ~産後2ヵ月までの期間にパパができることを、時期ごとにわけて解説します。
産後すぐ
出生後~7日頃までは、赤ちゃんとママは入院しています。
この時期に育休を取ると、上のお子さんの世話や、出産後に必要な書類の記入や提出をすることができます。
特に上のお子さんは、ママと数日間離れてストレスを感じていたり、さみしい思いをしているかもしれません。
上のお子さんのフォローも、パパの大切な役割です。
産後1週間
多くの場合、産後1週間経つとママと赤ちゃんが退院して自宅に帰ってきます。
パパは退院時の付き添いや荷物運び、赤ちゃんの世話などや家事を行い、退院後の生活のサポートをしましょう。
産後2~3週間
病院によっては、この時期に産後2週間健診があります。赤ちゃんの発達の状況やママの身体と心の状態を確認する大切な健診です。健診の付き添いにパパがいると、受付中の赤ちゃんの対応や荷物運びなどの通院のサポートができて、ママが助かります。
産後1ヵ月
生まれて1ヵ月経つと、産後1ヵ月健診があります。2週間健診のときと同様に、健診の際にパパのサポートがあるとママが安心できます。
また、お宮参りをするのもこの頃です。お宮参りをする神社の選定や、お宮参り後に会食をする場合は会場の手配や祖父母への連絡などを行い、ママと協力して行事をすすめましょう。
産後2ヵ月
産後2ヵ月は、出産後から続いている頻回授乳や夜泣きなどにより、ママの疲れがピークになりやすい時期です。
また、産後うつ病を発症するリスクの高い時期でもあります。
パパは夜泣き対応や夜間の授乳を交代して、ママがゆっくり休めるようにしましょう。
産後パパ育休とは別に育休も2回に分割して取れる
従来育休は、子どもが1歳になるまでの期間に1回取得できる制度でしたが、2022年の法改正により2回にわけて取得できるようになりました。
つまり、産後パパ育休と合わせると、子どもが1歳になるまでの間に最大4回(産後パパ育休2回+育休2回)まで育休を取得できます。
ママの体調や育児の状況をみながら育休をとり、ママをサポートしましょう。
まとめ
今回は、産後パパ育休の活用方法について解説しました。
産後パパ育休は、子どもの出生直後からパパが育児に関われる画期的な制度です。
制度を上手に活用すればママの負担を軽くできるだけでなく、赤ちゃんとの絆形成にも役立ちます。
赤ちゃんと過ごす時間は、一生のうちでほんのわずかです。だからこそ、育児のスタートをパートナーと分かち合うことは、かけがえのない体験になるはずです。
制度について正しく理解し、家庭にとって最適な育児環境を整えましょう。
参考:
・育児休業特設サイト 令和3年改正法のポイント|厚生労働省
・令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法の概要について|厚生労働省
・育児給付の概要|厚生労働省
・妊娠中の標準的な健康教育|日本助産師会
・関連する母子事業について|厚生労働省
・こころの耳 産褥期うつ病|厚生労働省